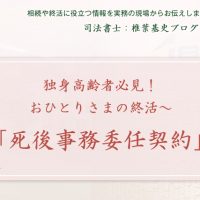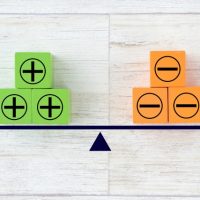今回は、本相続法改正の中では少し理解の難しいものの一つ、「遺産分割前の財産処分についての取扱いに関する改正」についてお話させていただきます。
1.これからの遺留分請求の方法は?
まず、用語について整理します。
今回の相続法の改正で、遺留分の請求は、相続財産の強制的な共有(所有)化を廃止し、遺留分を侵害している価額分の金銭請求を原則とすることとなりました。
それに伴い、これまでの「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」へと言葉を変えることになりましたのでご注意ください。
では、具体的にどういった流れで請求を行うことになるのか法的に整理していきたいと思います。
2.時効の整理
遺留分請求を行うにあたり、注意すべきものが時効になります。
これまでも、遺留分減殺請求権を行使するにあたっては、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年もしくは、相続開始から10年」で時効にかかるとされていました(改正前民法第1042条)。
これについては、今回の改正でも基本的に引き継がれています(改正民法第1048条)。
しかしながら、遺留分請求を行う旨の意思表示をしてから先の流れが大きく変わってきますので注意が必要です。
改正前であれば、遺留分減殺請求を行使する旨の意思表示をすれば、遺留分に抵触する一定の生前贈与(死因贈与含む)や遺贈は自動的に無効となり、強制的に、行使した相続人側が相続財産に持分を有する(所有化)こととなっていました。
したがって、一旦遺留分減殺請求の意思表示を時効期間内にしてしまえば、それ以降は時間をかけて相続財産の具体的な引き渡し(名義変更含む)を求めて裁判等を行っていたというわけです。
既に所有権化していますので引き渡しに時効はありません。
これが今回の改正では、相続財産の半強制的な共有化ではなく、侵害している金額の金銭請求に変わりましたので、遺留分請求を行った側は所有権ではなく、金銭債権を有することにかわりました。
民法には債権について「時効消滅」という考え方があり、一定の期間内に回収をすることが法律上求められるのです。
したがって、今後の遺留分請求については、遺留分請求をした後は、この金銭債権については時効期間内に回収しなければなりません。
これまでは、一旦遺留分減殺請求の意思表示をすればそれ以降は時効もなく引き渡しを求めるだけだったのが、一定の時効期間内での回収が必要となったため、うかうかとはしていられなくなったのです。
これは、請求を受ける側としてはある意味有利になった点ではあります。
ちなみに、この消滅時効の期間については、今後債権法の改正(2020年4月1日施行予定)が予定されており、現行の民法では、遺留分侵害額請求権を行使してから10年で時効となり(現行民法第167条参照)、改正後は5年となりますので注意が必要です(改正後民法第166条)
どちらの時効を取るかは、「遺留分侵害額請求権の行使時期」を基準とすると考えられていますので、仮に相続の開始が債権法改正前であっても、遺留分侵害額請求権の行使時期が債権法改正後であれば時効は5年となりますので、しっかり時効期間について整理をしておきましょう。
今後は、遺留分請求の時効(改正後民法第1048条)と、金銭債権化した後の消滅時効(改正前民法第167条、改正後民法166条)の2段階で時効を考える事になりますので、遺留分を請求する側は、しっかりとしたアクションを起こしていくことが求められます。
また、遺留分侵害額請求を受けた側は、請求を受けたときから原則延滞となり、支払の時期を伸ばせば伸ばすほど一定の損害金も付加されて請求されてしまいますので、その点もご注意ください。これについては、改正後民法では救済措置が用意されており、遺留分侵害額請求を受けた側は、支払時期について裁判所に一定期限の許与(猶予)を求めることができることとされました(改正後民法第1047条参照)。ただし、期限を許与された場合は、その分消滅時効のスタート時期もずれ込むことになります。
3.遺留分侵害額の算定方法は?
遺留分請求できる価額の算定方法については、これまで民法には具体的な規定がなく判例理論に基づいた計算がなされてきました(最判平8年11月26日判例、最判平10年2月26日判例参照)。
改正相続法ではこれまでの判例理論を条文として明確化することになりました(改正後民法第1046条参照)
具体的に、遺留分侵害額を求める計算式は以下のとおりです。
-
【遺留分を求める計算式】
- ①遺留分
=〈遺留分を算定するための財産の価額(贈与及び遺贈も含む)〉
×1/2(※)×〈遺留分権利者の法定相続分〉
※直系尊属のみが相続人である場合には、1/3 - ②遺留分侵害額
=〈遺留分〉-〈遺留分権利者の特別受益の額〉
―〈遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額〉
+〈遺留分権利者が相続によって負担する債務の額〉
ここで計算を行うにあたりいくつかの注意点があります。
まず、①で「遺留分を算定するための財産の価額(贈与及び遺贈も含む)」の金額を計算するにあたり、生前の贈与をどこまで遡るのかについてこれまでも色々な判例上の議論がありました。
これまでの判例理論では、相続人以外の第3者への贈与は「相続開始前1年」に限り(改正前民法第1030条参照)、相続人への贈与は期間制限無く無制限に遡ることとされていました(最判平10年3月24日判例参照)。
こういった考え方もあり、これまでは相続人ではなく相続人以外のものへの贈与が遺留分対策として有効だとされていたわけです(例えば、孫に対する贈与等)。
今回の改正では、相続人への贈与については期間制限が設けられ、「相続開始前10年」まで遡ることとされました(改正後民法第1044条参照)。
したがって、もし今後特定の相続人に他の相続人より多額に資産を承継させたい場合は、生前早い段階から贈与をすることにより、相続人への贈与であっても一定の遺留分対策ができることになりました
。
地味な改正ですが、実務上影響が大きいものになりますので、しっかり押さえておきましょう。
4.遺留分侵害額請求を受ける受遺者、受贈者の順番は?
前項3.で算定した遺留分侵害額請求権については、遺留分権利者は無制限にどの受遺者、受贈者に対しても請求できるわけではなく、一定のルールがあることに注意が必要です。
これまでも遺留分減殺請求できる対象となる遺贈や贈与については一定のルールがありました。
これについては、今回の改正においては実質そのまま維持されています(改正後民法第1047条参照)。
具体的には、以下の優先順位となります。
-
【遺留分を求める計算式】
- ①受遺者(遺贈を受けた者)
- ②受贈者(贈与を受けた者)
※受遺者が複数いる場合は、遺贈の目的の価額の割合に応じて按分する(遺言で変更可能)。
受贈者も同様の考え方である。
※②の贈与については、直近の贈与を受けた者が先に遺留分を負担しなければならない
したがって、①への請求で遺留分侵害額全てが計算上回収可能である限りは、受贈者への請求はできませんのでご注意ください。
これは、改正前と同様となっています。
更には、前述の3や上記②の注釈のとおり、遡る特別受益(生前贈与)は「相続開始前10年」でかつ、請求の順番は「直近の贈与が先」とされていますので、早く財産の承継を開始すればするほど遺留分請求を受ける可能性は低くなってくると考えられます。
5.現場での対応
以上のとおり、今回の改正によって、遺留分を請求する側としては、請求後の時効の管理が重要となり、また逆に遺留分請求対策を行う際には、より生前の早い段階における贈与の重要性が増すこととなりました。
それぞれの立場で今回の改正がどういった影響を与えるのかを整理し、適切に行動を起こしていくことが求められます。
特に生前の遺留分対策においては、孫(相続人以外)への贈与だけでなく、早い段階からの息子(相続人)への贈与も有効であることは大きな変更点です。
尚、遺留分制度に関する改正については、2019年7月1日より施行され、制度がスタートしています。