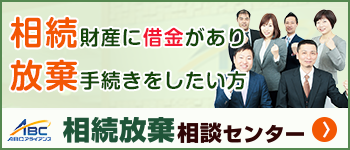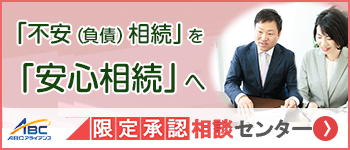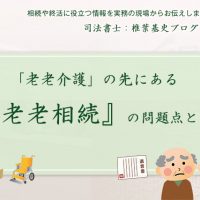近年、生涯独身率や熟年離婚も増えているため、一人暮らしをしている高齢者は増加傾向にあります。家族や親しい親族が近隣に住んでいれば良いですが、遠方に住んでおり疎遠であるというケースも少なくないでしょう。
そのような方が、入院が必要になった時や介護施設などへの入居を希望される時、身元保証人が見つからずに困るケースは珍しくありません。こうしたニーズの高まりもあり、身元保証の代行サービスを提供する民間企業も増えています。
ひとり身で終活を行っている方の中には、身元保証サービスへの加入を考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、健康であるし介護施設へ入居する予定もないという方の場合、身元保証人がいないことでどのようなリスクが想定されるのでしょうか。
また、身元保証サービスを巡るトラブルは決して少なくありません。消費者庁によると、約束していたサービスが受けられない、解約時に返金されないといった被害が報告されているようです。こうした被害に遭わないためにはどうしたら良いのでしょうか。
今回は、身元保証サービスの概要、終活で身元保証サービスの検討が必要なケース、身元保証人がいない場合のリスク、身元保証サービスの具体的な内容、身元保証サービスの費用、身元保証サービスの選び方と注意点などについて解説します。
【 目次 】
1.身元保証サービスとは
最近、ニーズの高まりから増加している身元保証サービスですが、具体的にどのような内容なのでしょうか。
(1)身元保証人とは
身元保証人は、身元を保証する人のことをいいます。雇用の際などに、身元保証人を立てるように求められた覚えがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。身元保証人は身元を保証するだけでなく、緊急時の連絡先となる他、本人が会社に故意や過失によって損害を与えた時に本人と連帯して賠償の責任を負うこともあります。
(2)高齢者が身元保証人を求められるケース
高齢者が身元保証人を求められるのは、主に入院の際と介護付き有料老人ホームや高齢者住宅などの施設への入居の際です。
入院や施設への入居の際に身元保証人が必要になる理由としては、主に以下のような事項が挙げられます。
- 緊急時の連絡先
- 金銭保証
- 本人死亡時の遺体と遺留品の引取
- 認知症になった時のため
身元保証人は家族や近しい友人にお願いすることが多いですが、適当な相手がいないという方もいらっしゃるでしょう。上述の項目からおわかりいただけると思いますが、身元保証人が負う責任は決して軽いものではありません。中には「迷惑をかけないから名前だけ貸してくれ」などといって、遠い親戚や友人に身元保証人になってもらう方もいらっしゃいますが、それでは後々トラブルになりかねません。
では、身元保証人が見つからない方はどうすれば良いのでしょうか。
このような悩みに応えて誕生したのが、高齢者向けの身元保証サービスです。
(3)高齢者向け身元保証サービスとは
高齢者向けの身元保証サービスは、身元保証を頼む相手がいない高齢者の身元保証を代行するサービスです。入院時や高齢者施設への入居の際の身元保証の他、見守りや健康相談、病院や施設の見学の際の付き添いなどの日常生活のサポート、死亡時の身元の引き受けや葬儀などの死後事務手続き代行などを行っている業者もあります。
2.終活で身元保証サービスの検討が必要なケース
終活で身元保証サービスへの加入の検討が必要と思われるのは、以下のようなケースが挙げられます。
- 独身、天涯孤独
- 家族が遠方に住んでいて頼りにくい
- 疎遠な親族に迷惑をかけたくない
このような方は、いざ身元保証人が必要になった時に頼むことができる相手がいないのではないでしょうか。親しくしている近所の方や友人などに頼むということも考えられますが、高齢者の場合、周囲の方も高齢であることが多いかと思います。高齢者が高齢者の身元保証人になることは、あまり得策ではありません。いざという時に健康上の問題から手続きができないケースや、身元保証人が亡くなってしまうというケースも起こりえるからです。同様に、家族がいらっしゃる方でも、夫婦や年の近いご兄弟を身元保証人にすることはおすすめできません。
高齢でも健康なら身元保証人など必要ないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、もしご自身が亡くなった時に身元保証人が身近にいない場合、疎遠になっている親族などに連絡が行き、迷惑をかけてしまうという可能性があります。また、健康に自信があったとしても、急病や認知の衰えが起きる可能性は否定できません。
そのような際の保険として、身近に頼ることができる相手がいない方は、終活の一環として、身元保証サービスの利用を検討した方が良いかもしれません。
3.身元保証人がいない場合のリスク
身元保証人がいない場合のリスクとして、介護が必要となり、高齢者施設などに入居しようとした際に、身元保証人がいないと断られてしまうことが多いということが挙げられます。データによると高齢者施設の90%以上が、入居の際に身元保証人を求めるといわれています。
また、入院や手術の際に身元保証人がいないばかりに、必要な医療が受けられないというリスクもあります。本来、医療については正当な理由なく診療治療の求めを断ることはできないとされています。しかし、実際は、身元保証人がいない場合は診療を断られるケースもあるようです。支払いの保証や医療行為への同意、緊急時の身元引受などの問題から、身元保証人がいない患者を受け入れることは医療機関側のリスクが高いからです。
また、身近に頼る相手がいないと様々な問題が起きる可能性があります。例えば、独居の高齢者が認知症を患ったことで、そこに付け込んだ業者によって高額契約を交わしてしまう事例は後を絶ちません。他にも身体の自由が利かなくなることで、自宅がゴミ屋敷化してしまうことや、食事や入浴といった日常行為が適切に行えなくなるというリスクもあります。日常的に頼れる身内がいない高齢者の場合、周囲の人間が気付いた時にはのっぴきならない事態に陥っているというケースは珍しくないのです。
こうした事態を避けるためにも、身近に頼れる相手がいない方は終活で身元保証サービスの利用を検討しても良いかもしれません。
4.身元保証サービスの具体的な内容
身元保証サービスの具体的な内容は、運営している業者やオプションによって異なりますが、主に以下のようなサービスを提供していることが多いです。
(1)身元保証
入院や施設の入居時の緊急時の連絡先となり、身元保証を行います。身元保証には、死亡時の医療機関や施設への支払い、身柄の引き取りなども含まれます。
(2)日常支援
日常支援は、定期連絡や訪問による見守り、緊急時の駆け付け、病院受診、施設入居前の見学、買い物などの外出への同行、入院時の手続きや着替え等の準備のサポート、自宅の郵便物の管理などが挙げられます。
日常支援の内容については、業者によって異なるため、詳細を確認する必要があります。基本料金内で日常支援を受けられるサービスもありますが、利用ごとに費用が発生するケースもあるので、料金についても確認しましょう。
(3)法律支援
身元保証サービスを行う業者の多くは、弁護士や司法書士など法律の専門家による支援を行っています。本人に代わって業務を代行するためには法律に基づいた契約を交わす必要があるため、高齢者の身元保証サービスには法的なサポートが欠かせないのでしょう。
法律支援として、オプションで任意後見契約を行っている業者も存在します。任意後見契約は、本人が将来認知症などで判断能力が低下した時の成年後見人を指定しておく契約です。この契約を交わしておくことで、万一認知症などで判断能力が低下した時に、業者が紹介する弁護士などに成年後見人となってもらうことができます。
他にも、財産管理や事務処理が難しくなった方のために、弁護士や司法書士などの専門家が金銭管理や日常的な事務処理を代行する民法上の契約業務を行っている業者も存在します。
(5)葬儀・納骨、死後事務代行など
身元保証人を必要とする高齢者の多くは、身寄りがない、身内に頼りたくないという方が多いため、亡くなった時の病院や施設からの身元の引き受けと併せて葬儀や納骨までを全てセットとして依頼したいという方が多いのではないでしょうか。そのようなニーズに応えて、葬儀や納骨までを引き受けている業者も多く存在します。
他にも、人が亡くなった後には様々な手続き(役所・関係機関への連絡、年金の停止、医療機関や施設への未払い分の清算、遺品整理や住居の処分等)が必要となります。当然、こうした死後事務も併せて依頼したいと考える方も少なくないと思います。しかし、死後事務作業については専門性が高く業務内容も多岐に渡るため、採算が取れないことから、対応していない業者も多いです。死後事務作業を全て依頼したいという方は、依頼先を検討する際に、どこまで対応してもらえるのかしっかり確認することが大切です。
5.身元保証サービスの費用
身元保証サービスの費用は、運営元の会社やプランなどによって大きな差があります。
参考として、公式サイトに費用を掲載している会社2社を比較してみましょう。
| A社 | B社 | |
|---|---|---|
| 入会金 | 10万円 | 15万円 |
| 会費 | 1万円(年額) | 5000円(月額) |
| 身元保証料 | 約35万円(預託金) | 27万円5千円 |
| 葬儀・納骨 | 約50万円 | 27万5千円 |
| その他 | 事務管理費:約54万円 | 万一の支援費用:16万5千円 |
| 生活支援(都度) | 3500~円 | 3300~円 |
全ての費用を合計すると、それなりの金額になることがわかります。
また、身元保証サービスの会社全般に言えることですが、費用体系が入会金、年会費、預託金、事務管理費、生活支援費(都度)等、細かく刻まれているため、実際にいくらかかるのかわかりにくいという特徴があります。
そのため、最初に説明を受けた時と見積もりを出してもらった時の金額が大きく異なるというケースは珍しくありません。希望していないオプションを勝手に付けられていた、必要としていたサービスが含まれていなかったなどというトラブルも多く報告されています。
身元保証サービスは高額な契約になりますので、慎重に内容や料金を確認した上で選ぶことが大切です。
6.身元保証サービスの選び方と注意点
身元保証サービスを選ぶ際、どのようなポイントに注意して選べば良いのでしょうか。
前述した通り、身元保証サービスは、会社やプランによって費用が大きく異なります。そのため、費用を比較して、できる限り安いサービスを選びたいという方もいらっしゃるかもしません。しかし、身元保証サービスを選ぶ際には、費用に惑わされずにサービス内容の詳細をしっかり確認することが大切です。
自分に合ったサービスを選択するためにも、まずは、自分がどのようなサービスを受けたいかを明確にしましょう。自分にどのようなサービスが必要かわからない場合は、検討の段階で専門家に相談してみるのも良いでしょう。
また、契約時には、面倒がらずに契約書を全て読み、内容を理解することが大切です。字が小さくて読みづらいという場合は、周りの人間に読んでもらうことをおすすめします。
後々のトラブルを防ぐために、預託金がある場合は使用用途について、また万一の時に備えて解約時の返金等に関する条件についても確認しておくことをおすすめします。
また、契約書に記載された内容を確実に履行してもらうために、契約書は公正証書で作成することをおすすめします。
まとめ
今回は、身元保証サービスの概要、終活で身元保証サービスの検討が必要なケース、身元保証人がいない場合のリスク、身元保証サービスの具体的な内容、身元保証サービスの費用、身元保証サービスの選び方と注意点などについて解説しました。
様々な事情からおひとりさまが増加している昨今ですが、若く健康なうちは特に問題がなくても、高齢になるとどうしても誰かを頼らざるを得ない場面というのが増えていくのが現実です。弱った時に頼る相手がいないというのは心細いものですが、今回ご紹介したような身元保証サービスを利用すれば、もしもの時の安心保障となります。終活の際に検討してみてはいかがでしょうか。