会社からお金を借りることができる従業員貸付制度は、急な資金ニーズに対応するための便利な制度です。
福利厚生の一環として提供されるこの制度は、低金利での借入や社内での審査完結、給与天引きによる返済など、従業員にとって多くのメリットがあります。
しかし、利用にあたっては連帯保証人の必要性や返済期間・借入金額の制限などの注意点も存在します。
本記事では、従業員貸付制度の基本的な仕組みからメリット、注意点、利用の流れまでをわかりやすく解説し、賢く借入するためのコツを紹介します。
目次
会社からお金を借りる「従業員貸付制度」とは

従業員貸付制度は、企業が福利厚生の一環として自社の従業員に資金を貸し付ける制度です。
急な支出や一時的な資金不足に対応できるため、金融機関よりも低い金利で借りられる点が大きなメリットです。
従業員貸付制度の概要
- 定義:企業が従業員に対し、福利厚生の一環として低金利で資金を貸し付ける制度。
- 目的:従業員の生活支援や急な出費への対応、働きやすい環境づくり。
- 利用対象:主に正社員が対象で、契約社員やパート・アルバイトは対象外とする企業が多い。
- 貸付限度額:勤続年数や役職、会社規定によって異なる。
- 金利:2.0~4.0%程度が一般的ですが、会社によって異なります。
- 審査:社内で行われ、勤務態度や勤続年数、借入理由などを総合的に判断。
- 必要書類:社内規定の申請書が主で、詳細は会社ごとに異なります。
- 返済方法:給与天引きや口座引き落としが一般的。
主なメリット
- 金融機関より低金利で借りられる
- 信用情報に影響しない
- 総量規制の対象外で、まとまった金額も借りやすい
- 審査が比較的簡易で、返済は給与天引きが多い
注意点・デメリット
- 退職時に一括返済を求められる場合がある
- 返済の延滞や滞納は人事評価に悪影響を及ぼす可能性がある
- 利用対象や貸付条件は会社ごとに異なり、必ずしも全ての従業員が利用できるわけではない
- 無利息での貸付は贈与税の課税対象となるおそれがあるため、一定の金利が設定されている
申請や利用条件、返済規定は必ず社内規定を確認してください
従業員貸付制度を利用するメリット
以下では、従業員貸付制度を利用する3つのメリットについて、詳しく解説していきます。
低金利で借りられる
従業員貸付制度の最大の特徴は、一般的な金融機関よりも低金利で資金を借りられる点です。
制度によっては年0.9%~4.0%程度の金利が設定されており、消費者金融や銀行カードローン(年1.5%~18.0%程度)と比べて利息負担が大幅に軽減されます。
この低金利は、会社が営利目的ではなく従業員の生活支援を目的としているため実現しています。
審査が社内で完結し、信用情報に影響しない
従業員貸付制度は社内の手続きで完結するため、外部の信用情報機関に利用履歴が登録されることはありません。
また、審査も社内規定に基づいて行われるため、金融機関のような厳格な与信審査はなく、比較的柔軟に対応される傾向があります。
ただし、会社ごとに審査基準や手続き期間は異なり、実際の融資まで2~3週間かかる場合もあります。
返済は給与天引きで手間がかからない
返済は給与天引きで行われるのが一般的であり、返済忘れのリスクが少なく、計画的な返済が可能です。
また、総量規制の対象外のため、他の借入があっても利用しやすい点もメリットです。
従業員貸付制度の注意点と上手な活用法

従業員貸付制度は多くのメリットがありますが、利用にあたってはいくつかの注意点も理解しておく必要があります。制度を効果的に活用するためには、デメリットを把握し、適切な使い方を心がけることが重要です。
連帯保証人が必要な場合がある
多くの企業では、従業員貸付制度の利用に際して連帯保証人を求めることがあります。
これは、借入者が返済不能となった場合に備えたリスク管理の一環です。連帯保証人は借入者の返済義務を肩代わりする責任を負います。
連帯保証人を依頼する際は、信頼できる人物を選ぶことが大切です。社内の先輩社員や上司、または家族や親戚に相談する方法がありますが、いずれの場合も返済計画を明確に伝え、双方の理解を得ることが必要です。
返済期間や借入金額に制限がある
従業員貸付制度には、返済期間や借入金額の上限が設定されていることが一般的です。
例えば、返済期間が最長5年、借入限度額が100万円といった制限がある場合があります。これらの制限は会社の資金管理やリスク管理のために設けられています。
必要な金額や返済期間が制度の範囲を超える場合は、他の社内制度の併用や金融機関からの借入れを検討することが推奨されます。また、返済計画の見直しや支出の節約も重要な対策です。
計画的な返済を心がける
従業員貸付制度は低金利で利用しやすい反面、安易な借入れは返済負担の増加やトラブルの原因となります。返済に苦しむケースも報告されているため、無理のない返済計画を立てることが不可欠です。
返済額は手取り収入の20%以内を目安に設定し、借入目的を明確にして必要最低限の金額を借りることが望ましいです。また、他の借入れとのバランスを考慮し、計画外の支出を控えるなど生活面の工夫も返済成功の鍵となります。
従業員貸付制度は緊急時の資金調達手段として有効ですが、最後の手段として計画的に利用することが重要です。
従業員貸付制度の利用の流れと必要書類
従業員貸付制度を利用する際は、まず自社に制度があるかどうかを確認することが重要です。
制度がある場合は、人事部や総務、経理担当に問い合わせて利用条件や必要書類を確認し、申請書類を提出して社内審査を受けるという流れになります。
自社に従業員貸付制度があるか確認する
従業員貸付制度は福利厚生の一環として多くの企業で導入されていますが、すべての会社にあるわけではありません。
会社の就業規則や福利厚生の資料を確認し、見つからない場合は人事部や総務に直接問い合わせましょう。制度は「社内融資」「社内ローン」など別の名称で呼ばれることもあります。
厚生労働省の調査によると、従業員1,000人以上の企業での導入率は約34.5%、100人~999人規模では14.5%、100人未満の小規模企業では5.6%と、企業規模によって導入率に差があります。
利用条件や必要書類を人事部に問い合わせる
制度の有無が確認できたら、次に利用条件や必要書類を詳しく確認しましょう。主な確認ポイントは以下の通りです。
-
貸付限度額:多くの場合、月収の数ヶ月分程度が目安ですが、会社によって異なります。上限は一般的に100万円程度までのケースが多いです。
-
貸付金利:無利息の会社もありますが、一般的には1%~5%程度の低金利が設定されています。
-
返済期間:1年~5年程度が一般的で、返済方法は給与天引きが多いですが口座振替の場合もあります。
-
必要書類:申請書、誓約書、給与明細、場合によっては住民票や収入証明書、見積書や領収書の提出を求められることがあります。
必要書類は会社ごとに異なるため、事前に人事部に確認し、準備を進めることがスムーズな申請につながります。
申請書や契約書を提出し、社内審査を受ける
申請書には氏名、所属、希望借入金額、返済期間、借入目的(生活費、教育費、冠婚葬祭費など)、返済方法(給与天引き、口座振替など)、連帯保証人の有無などを記入します。
誓約書や給与明細、必要に応じて住民票などと共に提出します。書類の不備があると審査に通らない場合があるため、記入漏れや誤記に注意してください。
社内審査では、勤務年数や勤務態度、借入目的の妥当性、必要書類の有無などが確認されます。
審査に通過すると、金銭消費貸借契約書(借用書)を交わし、貸付条件を確認のうえ契約します。契約後、指定口座に貸付金が振り込まれます。
申請から融資までの期間は会社によりますが、一般的には数日から1週間程度かかることが多く、即日融資には対応していません。
まとめ
従業員貸付制度は、低金利で利用しやすい資金調達手段として多くの従業員にとって心強い制度です。
しかし、連帯保証人の必要性や借入金額・返済期間の制限など、注意すべきポイントもあります。利用前には自社の制度内容をしっかり確認し、計画的な返済を心がけることが重要です。
本記事で紹介したポイントを参考に、従業員貸付制度を賢く活用し、安心して資金を借り入れましょう。
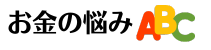


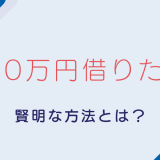
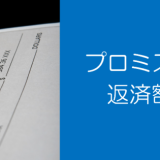
コメントを残す