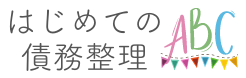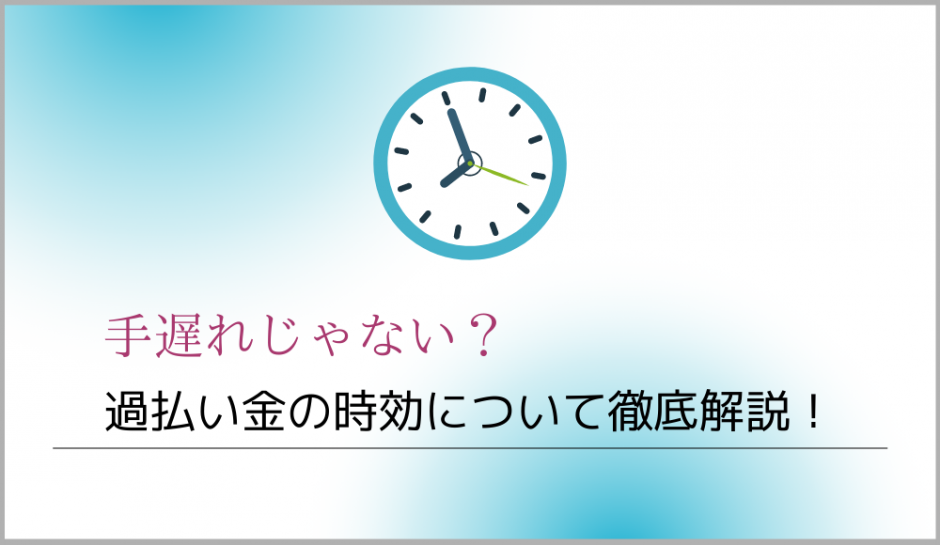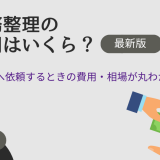過払い金請求をしてみたいと思っていても、いつまでそれが可能なのか気になるところです。
この点について、刑事事件などでよく聞く「時効」の制度と関係します。
過払い金請求の時効は、完済日や権利を知った日によって変わりますが5年または10年となります。
ただし、取引の分断や時効中断など、細かい判断が必要な場合もあるため、早めに専門家に相談することが大切です。
この記事では、過払い金の時効についてはもちろん、詳しい法律の内容などをお伝えします。
目次
過払い金の時効とは何か
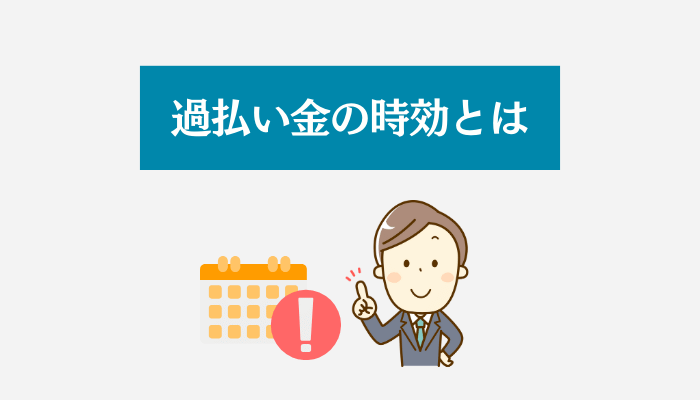
過払い金の返還請求権には消滅時効があり、一定期間を過ぎると請求できなくなります。過払い金の時効については、2020年4月1日に施行された民法改正でルールが変わりました。
時効とは
時効とは、一定の期間が経過した場合に、法律上の権利を取得したり、逆に権利が消滅したりする制度です。
民法上、時効には「取得時効」と「消滅時効」があり、過払い金請求で問題となるのは消滅時効です。
消滅時効は、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅する制度です。過払い金返還請求権も債権の一種であり、消滅時効の対象となります。
- 2020年3月31日以前に完済した場合は、完済日から10年で時効
- 2020年4月1日以降に発生した過払い金については、「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で時効
古い情報で「過払い金の時効は10年」とだけ説明しているものもありますが、現在は5年のケースもあるため注意が必要です。
参照元:法務省「消滅時効に関する見直し」
時効が成立した場合
時効期間が経過しただけでは自動的に過払い金請求権が消滅するわけではありません。
貸金業者側が「時効の援用」を行うことで、初めて時効が成立します。時効の援用とは、「時効期間が経過したので返還請求に応じない」という意思表示のことです。
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
参照元:e-Gov法令検索「第百四十五条(時効の援用)」より
一部だけが時効になる場合
取引の途中で一度完済し、その後再度借り入れをした場合、取引が「分断」されたと評価されることがあります。
分断された場合、最初の取引分の過払い金についてのみ時効が成立することがあります。
完済後に再借入れまでの期間が長い場合や、完済時に解約手続きをした場合などは、分断と判断されやすくなります。
出資法改正後の過払い金請求
出資法が改正され、グレーゾーン金利が廃止されたのは2010年6月18日です。すでに10年以上経過していますが、過払い金の時効は「完済日」から起算されます。
そのため、完済時期によっては、現在も過払い金請求が可能なケースがあります。
過払い金請求とは不当利得に基づく返還請求のこと
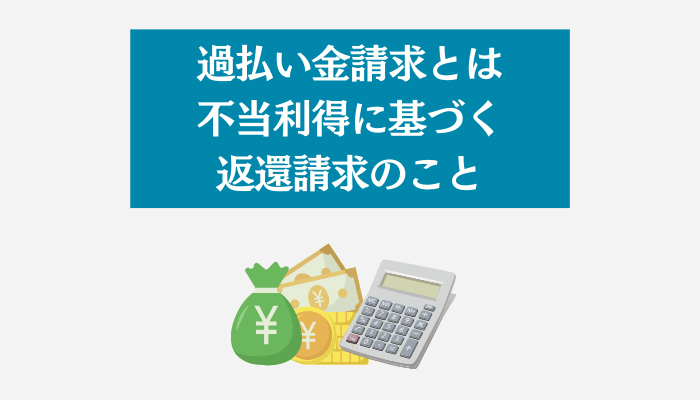
過払い金請求とは
過払い金請求とは、貸金業者に対して利息制限法で定められた上限利率を超えて支払った利息(いわゆる「グレーゾーン金利」部分)について、払い過ぎた分の返還を求める手続きです。
これは民法703条以下の「不当利得返還請求権」に基づいて行われます。
「毎月契約どおり返済していただけで返してもらえるお金なんか無いだろう?」と思う方もいるかもしれませんが、過払い金請求には明確な法的根拠があります。
利息の上限を定める法律
利息の上限を定める主な法律には、利息制限法・出資法・貸金業法の3つがあります。過払い金請求は主に利息制限法と出資法の上限利息の違い、そして法改正の経緯と関係しています。
利息制限法は、金銭消費貸借契約における上限利率を定めており、これを超える部分は民事上無効です。出資法は、上限利率を超える貸付をした場合の刑事罰を定めています。
利息制限法の上限利率
- 元本10万円未満:年20%
- 元本10万円以上100万円未満:年18%
- 元本100万円以上:年15%
参照元:利息制限法1条
出資法の上限利率の推移
| 期間 | 上限利率 |
|---|---|
| 昭和29年8月1日~昭和58年10月31日 | 109.5% |
| 昭和58年11月1日~昭和61年10月31日 | 73% |
| 昭和61年11月1日~平成3年10月31日 | 54.75% |
| 平成3年11月1日~平成12年5月31日 | 40.004% |
| 平成12年6月1日~平成22年6月17日 | 29.2% |
| 平成22年6月18日以降 | 20% |
グレーゾーン金利とは
「グレーゾーン金利」とは、利息制限法の上限利率(年15~20%)を超えているが、出資法の上限利率(かつては年29.2%)を超えない範囲の金利を指します。
この金利帯での貸付は、民事上は無効ですが、刑事罰の対象にはならなかったため、多くの貸金業者が利用していました。
かつては「みなし弁済規定」により、一定の要件を満たせば利息制限法を超える利息の受け取りが有効とされていましたが、最高裁判例や法改正により、実際にはほとんど認められなくなりました。
参照元:愛知弁護士会
最高裁判所の判断
最高裁判所は、以下のような判断を示しています。
- 利息制限法を超える利息を支払った場合、その超過分は元本に充当される
- 元本が完済された後に支払った金額は、不当利得として返還請求ができる
このような法解釈により、払いすぎた利息を取り戻すことが可能となりました。
具体例
例えば、50万円を年利25%で借りていた場合、利息制限法の上限(18%)を超える7%分はグレーゾーン金利となります。この超過分は元本に充当され、元本完済後に支払った分は過払い金として返還請求が可能です。
※参照元:最高裁判所判例集
過払い金請求の内容
過払い金請求ができる場合、主に以下の内容を請求することができます。
- 支払った過払い金の元金
- 元金に対する利息
支払った過払い金の元金
利息制限法の上限を超えて支払った利息部分(グレーゾーン金利相当分)は、不当利得返還請求権として元金の返還を請求できます。
元金に対する利息
過払い金の元金に加えて、民法上の法定利率に基づく利息も請求できます。利息の利率は、過払い金が発生した時期によって異なります。
- 令和2年(2020年)3月31日までに発生した過払い金については年5%
- 令和2年(2020年)4月1日以降に発生した過払い金については年3%
過払い金が発生した時期が改正前後にまたがる場合は、原則として発生時点ごとに適用利率が異なりますが、ほとんどのケースでは年5%が適用されることが多いです。
また、貸金業者が「悪意の受益者」とみなされるため、ほとんどの場合で利息を付して返還請求が認められます。
発生した過払い金がすべて戻ってくるわけではないので注意
過払い金として元金や利息を請求できても、実際に全額が戻ってくるとは限りません。
どの程度の金額を返してもらうか、また返還時期などは、業者の対応や交渉・訴訟の進め方によって大きく異なります。自分で請求する場合は返還率がさらに低くなることが多いです。
任意交渉(話し合い)による場合
多くのケースで、貸金業者との交渉では過払い金元金の全額返還は難しく、返還率はおおむね40~90%程度にとどまります。
利息は交渉段階でカットされることが多く、元金のみの返還となる場合もあります。
業者によってはさらに低い返還率となることもあり、例えばアコムやプロミスでは80~90%、アイフルでは50%前後が目安とされています。
裁判を行った場合
訴訟を提起した場合、元金の全額返還や利息の上乗せが認められる可能性が高くなります。大手業者であれば、裁判で100%の元金返還や利息の支払いが認められる事例も多く見られます。
ただし、業者の経営状態や資産状況によっては、判決後に強制執行を行っても全額回収できないリスクもあります。
強制執行には、相手の資産を特定する手間やコスト、複数の請求者による競合などのリスクも伴います。
過払い金請求を行うための条件
過払い金請求を行うには、以下の条件を満たす必要があります。
- 利息制限法の上限を超える利率で借り入れをしていた
- 2010年6月18日以前に借り入れをしていた
- 借金を完済してから10年(または請求できることを知ってから5年)が経過していない
- 請求先の貸金業者が現存している
- 銀行やクレジットカードのショッピング利用分ではない
利息制限法の上限を超える利率で借り入れをしていた
過払い金は、利息制限法で定められた上限利率(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超える利率で借り入れをしていた場合に発生します。
利息制限法以内の利率で借り入れていた場合は、過払い金は発生しません。
2010年6月18日以前の借り入れである
2010年6月の法改正以降、グレーゾーン金利は廃止され、ほとんどの貸金業者が利息制限法の範囲内で貸付を行うようになりました。
そのため、2010年6月18日より前に借り入れをしていた場合に過払い金が発生している可能性があります。
完済から10年(または請求できることを知ってから5年)が経過していない
過払い金請求権には消滅時効があります。原則として「完済日から10年」または「請求できることを知った日から5年」のいずれか早い時点で時効が成立します。
時効が成立している場合、請求は認められません。
貸金業者が現存している
過払い金は貸金業者に対して請求する権利です。請求先の業者が倒産・消滅している場合、原則として過払い金請求はできません。
倒産した場合でも、破産手続きや会社更生手続き中であれば配当請求ができることもありますが、全額返還されるケースは稀です。
過払い金は、国から保障されるものではなく相手に対して請求するものなので、会社が今でも存在している(消滅していても対応してくれる)ことが条件
銀行カードローンやショッピング利用分ではない
銀行や信用金庫のローン、クレジットカードのショッピング利用分は、利息制限法の範囲内での貸付が行われているため、過払い金請求の対象にはなりません。
また、キャッシング枠で発生した過払い金があっても、ショッピング残高がある場合は相殺されるため、残高があるうちは過払い金請求はできません。
過払い金請求に専門家の依頼が必要な理由
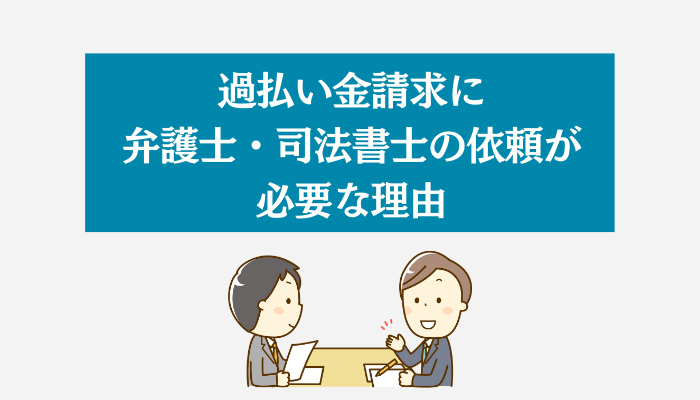
過払い金請求は原則として個人でも可能ですが、現実的には弁護士や司法書士への依頼が強く推奨されます。その主な理由を解説します。
複雑な計算と法的判断が必要
過払い金の正確な計算には「引き直し計算」が必要です。これは利息制限法に基づき、過去の取引履歴を日単位で再計算する作業で、以下の要素が含まれます。
- うるう年(366日計算)の扱い
- 取引の分断(借り直しの有無の判断)
- ショッピング残高との相殺関係
- 法定利率の時期的適用(年5%→3%の切り替え時期)
専門家は専用ソフトと判例知識で正確な計算が可能ですが、個人では計算ミスのリスクが高くなります。
貸金業者との交渉力に差がある
返還率の違いとして弁護士依頼の場合 70~100%、個人交渉では40-80%が相場(例:アコム80~90%、アイフル50%前後)です。
対応スピードについても、専門家依頼で3~6ヶ月ですが、個人では1年以上かかるケースがあります。
そのほか、弁護士は「金融庁への報告」「訴訟提起」を根拠に効果的な交渉が可能なため、法的にプレッシャーをかけることができます。
訴訟対応が必要となる可能性がある
交渉が決裂した場合、以下の複雑な手続きが必要になります。
- 訴状作成(取引履歴・計算書の添付)
- 証拠説明書の作成
- 法廷での主張(平均5回以上の出廷)
- 強制執行手続き(財産差し押さえ)
弁護士はこれらの手続きを一括代行してくれます。
専門家に依頼した方が判決後の回収率も上がる
過払い金請求は弁護士・司法書士のいずれに相談すべきか
過払い金請求を弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか迷った場合、以下のポイントを押さえると適切な判断ができます。
弁護士と司法書士の違い
まず、弁護士と司法書士には対応可能金額や訴訟権限が異なります。
手続きの制限事項
| 専門家 | 対応可能金額 | 訴訟権限 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 140万円まで | 簡易裁判所のみ |
| 弁護士 | 制限なし | 全ての裁判所 |
140万円超の案件や地方裁判所での訴訟が必要な場合、弁護士のみが対応可能
司法書士に依頼するメリット
弁護士に比べて簡易的な手続きに限られる司法書士ですが、費用が安価であるという大きなメリットがあります。
費用比較表
| 項目 | 司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料(90%の事務所) | 5,000-10,000円 |
| 基本報酬 | 3~6万円 | 4~8万円 |
| 成功報酬率 | 15~20% | 20~30% |
| 訴訟対応追加費用 | 不可 | 3~5万円 |
費用面の他には、簡易裁判所での手続きに特化・地域密着型の相談窓口が多いなどのメリットがあります。
選択の基準
権限や費用の違いを踏まえて、弁護士と司法書士のどちらを選択すべきか、選択基準を作成してみました。
- 140万円以下の案件:司法書士が費用対効果に優れる
- 140万円超の案件:弁護士のみ対応可能
- 複数社への請求:弁護士が一括管理可能
- 訴訟リスクの高い案件:弁護士が有利
具体的な事例
- アコムからの過払い金120万円請求 → 司法書士が適任
- 複数社から合計300万円請求 → 弁護士必須
- 武富士の後継会社への請求 → 弁護士の専門知識が必要
弁護士に依頼すべきケース
- 1社あたりの過払い金が140万円を超える
- 地方裁判所での訴訟が必要な案件
- 複数の貸金業者に跨る請求
- 業者が強硬な姿勢を示している
専門家選びのポイント
弁護士・司法書士ともに、専門家を選ぶ際は以下のポイントを抑えておくと確実です。
過去3年間で50件以上の処理経験がある
成功報酬制か着手金制か明示してくれる
事前調査なしで30分以上の相談が可能
主要貸金業者(アコム・プロミス等)との交渉経験あり
上記のポイントは無料相談の際に質問してみましょう。
過払い金請求に強いおすすめの法律事務所
- 弁護士法人・響
- 弁護士法人東京ロータス法律事務所
- 弁護士法人ひばり法律事務所
- 司法書士法人はたの法務事務所
- 弁護士法人ユア・エース
いずれの法律事務所も全国対応です
| 項目 | 弁護士法人・響 | 東京ロータス | ひばり法律事務所 | はたの法務事務所 |
|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 着手金 | 0円 | 22,000円~ | 0円 | 0円 |
| 成功報酬率 | 15~20% | 20~30% | 22% | 12.8% |
| 全国出張対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 女性専用ダイヤル | △ | ✕ | 〇 | 〇 |
弁護士法人・響

東京・大阪・福岡・沖縄に拠点を構える総合法律事務所です。債務整理や過払い金請求に強く、24時間365日無料相談が可能。
相談時は弁護士とスタッフが専任で対応してくれます。
顧客満足度は95%以上を維持。税理士や社労士との連携で複雑な案件にも柔軟に対応OK。
分割払いや費用の後払い制度があり、初期費用の負担が軽減されます。響グループ全体で多角的なサポートを行ってくれるのが強みです。
弁護士法人東京ロータス法律事務所

東京・上野を拠点とし、債務整理・過払い金請求に特化した法律事務所です。7,000件超の実績を誇ります。
全国出張相談や匿名対応でプライバシーを重視。返済プランの交渉に強く、最長8年の分割返済成功例があります。
債権者との信頼関係構築に長けており、スムーズな解決を実現。費用は着手金22,000円~と明確で、分割払いにも対応しています。
弁護士法人ひばり法律事務所

東京・錦糸町で25年以上の実績を誇る法律事務所です。過払い金請求は着手金0円・経費5,500円のみと低コスト。
女性専用ダイヤルを設けており、匿名相談や全国対応も可能です。高い顧客満足度をキープしています。
代理返済代行サービスを利用可能で金銭管理の負担を軽減。口コミでは、「費用対効果の高さ」が評価されています。
司法書士法人はたの法務事務所

東京・大阪で開業40年の老舗司法書士法人です。費用は業界最安値水準(基本報酬2万円/社)で、140万円以下の簡易裁判所案件を得意としています。
土日・夜間21時半まで相談可、女性スタッフが丁寧に対応してくれます。そのほか出張相談無料で分割払い・代行弁済にも柔軟に対応。
140万円超の案件は提携弁護士を紹介してくれます。
弁護士法人ユア・エース

東京・福岡を中心に17万件以上の債務整理実績を誇る大規模事務所です。オンライン面談に対応しており24時間相談受付OK。
弁護士20名以上のチーム体制で複数社への一括請求に強みがあります。成功報酬制で初期費用は0円、高額案件でも柔軟に対応してくれます。
まとめ
この記事では過払い金の時効を中心にお伝えしました。
過払い金は一定期間請求をしないと時効を迎えてしまいます。時効がいつ成立するかは、完済時期などによって異なります。
2020年民法改正後、時効期間が「完済から10年」から「請求可能認知後5年」に短縮されたため、早期の専門家相談が非常に重要です。