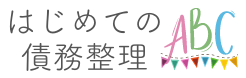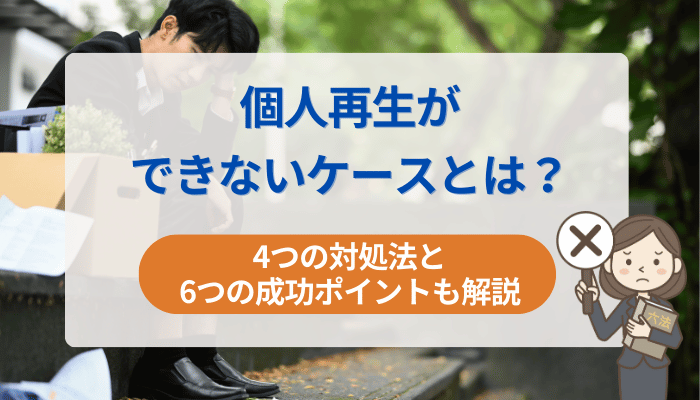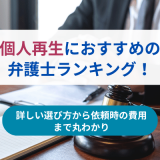個人再生は、財政的に困難な状況にある個人が、債務の整理と返済計画の立案により借金問題を解決させるための法的手段です。
しかし、この手続きは一定の条件を満たす必要があり、誰でも行えるわけではありません。
本記事では、個人再生ができないケースと、それに対する対処法について解説します。
個人再生におすすめの弁護士は以下の記事にまとめています。個人再生を検討中の方は、ぜひ参考にして下さい。
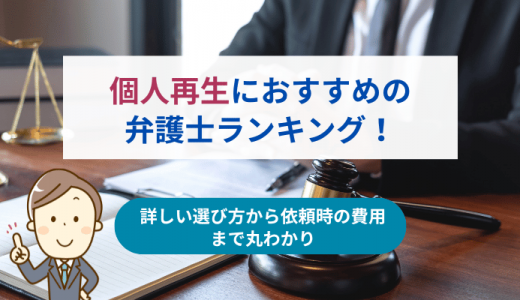 【2024年】個人再生におすすめの弁護士ランキング!詳しい選び方から依頼時の費用まで丸わかり
【2024年】個人再生におすすめの弁護士ランキング!詳しい選び方から依頼時の費用まで丸わかり
目次
個人再生ができないケースとは?
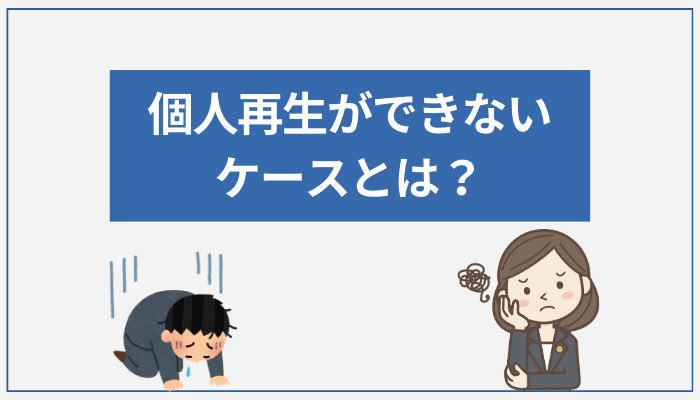
個人再生という法的な手続きは、借金問題を解決し、新たな生活をスタートするための一助となる手段です。しかし、全ての人が個人再生の対象となるわけではありません。
それは、法律が定める一定の条件や規則を満たしていない場合、個人再生手続きは難しいか、あるいは無理な場合があるからです。
借金の総額が5000万円以上
個人再生制度は、借金の総額が税金や保険料の支払いを除いて5,000万円以下の個人が対象となっています。
例外として、住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンの金額が5,000万円に含まれることはありません。
したがって、借金の総額が5,000万円を超えている場合、個人再生の手続きは難しくなります。その場合、他の法的な債務整理手段、たとえば自己破産などを検討することが求められます。
多額の財産を持っている
個人再生は、債務者が将来の収入から返済を行っていく方法です。多額の財産を持っている場合、その財産を使って借金を返済することが求められます。
具体的には、財産が多い人は弁済額が高額となります。そのため、多額の財産を持つ人が個人再生を行うことは難しいです。
弁済額が高額となると、返済のための収入も多く必要となります。
返済能力が全くない
個人再生は、債務者が一定の収入を有していて、その収入から借金を返済できる人が対象となります。
返済能力が全くない場合、個人再生は難しくなります。そのような状況では、一部または全ての債務を帳消しにする自己破産の手続きを検討することが適切かもしれません。
借入れの大部分が事業資金である
個人再生は主に消費者金融などの借金に対する手続きであり、借入れの大部分が事業資金となっている場合、適用が難しい場合があります。
保証人や担保物件が関わることが多く、これらが個人再生の手続きを複雑にするからです。
事業資金に関連する借金の場合、事業再生や会社の再生手続き、あるいは自己破産を検討する必要があります。
特定の債権者を優先させてしまった
個人再生手続きでは、すべての債権者が平等に扱われるべきです。特定の債権者だけを優遇する行為は、他の債権者の利益を損なうため、避けるべきです。
特定の債権者を優先させる行為は、偏頗弁済と呼ばれており禁止されています。
このような行為が明らかになった場合、個人再生の申し立ては却下される可能性があります。
不正行為や隠蔽行為があった
個人再生手続きは信頼と誠実さに基づいています。したがって、債務者が不正行為や隠蔽行為を行った場合、その手続きは否認される可能性があります。
これには、財産を隠す、所得を過少申告する、債務を過大申告するなどの行為が含まれます。
再度の借入れや無計画な支出を行った
個人再生手続き中に新たな借入れを行うことは避けるべきです。新たな借入れは返済計画を台無しにし、手続きをより困難にする可能性があります。
また、無計画な支出も避けるべきです。財務状況をさらに悪化させるだけでなく、裁判所からの認可を得る可能性を減少させます。
個人再生手続きは自己の経済状況を安定させ、再建するための手段であり、新たな借入れや無計画な支出はその目的に反する行為となります。
手続き途中で弁護士や司法書士の指示を無視する
個人再生手続きは法的な手続きであり、専門的な知識と経験が必要です。弁護士や司法書士の指示を無視することは、手続きの失敗につながる可能性があります。
専門家は最良の結果を得るための助言を提供してくれますが、その助言を無視すると、手続きが不完全になったり、裁判所からの認可が得られなくなったりする場合があるのです。
計画的な返済の意思が見られない
個人再生の申立てを行う際、返済意欲や返済計画の存在が大きなポイントになります。個人再生は借金の一部を免除し、残りを一定期間内に分割して返済する制度です。
そのため、確実に返済できる計画がなければ、裁判所は個人再生の認可を出さない可能性があります。
また、返済計画を立てる際は、自身の収入や生活費、その他の必要経費を考慮することが重要です。
不合理な返済計画を立てると、その後の生活が苦しくなるだけでなく、計画通りの返済が難しくなる可能性もあります。
借金返済のための計画をしっかりと立て、その計画を実行に移す意思が重要となります。
借金の総額が100万円以下
個人再生を選択する一つの目安として、債務の総額が一定の金額以上であることが挙げられます。借金総額が100万円以下の場合は最低弁済額が全額となり、個人再生で借金を減らすことができません。
通常、借金の総額が100万円以下という状況では、個人再生よりも任意整理を選択することが一般的です。
個人再生の手続きは比較的複雑であり、また裁判所の許可が必要であるため、手続きに時間と費用がかかるからです。
そのため、借金の総額が少ない場合、それだけで個人再生が適用できないというわけではありませんが、他の方法の方が適切である可能性が高いといえます。
小規模個人再生において債権者から反対される
個人再生は、小規模個人再生は給与所得者等再生から選択しますが、減額幅の大きい小規模個人再生を選ぶパターンが多いです。
ただし、小規模個人再生は一方的に債務者の利益だけを考えた手続きではありません。
実際には、債権者にも一定の権利があり、その一つが反対の申立てを行う権利です。
債務者が提案した返済計画に対して債権者が不満を持つ場合、債権者は決議に不同意を示すことができます。
債権者からの反対が認められた場合、個人再生の手続きは不成立となり、債務者は再度、債務整理の手段を選び直さなければなりません。
このため、借金返済に計画性を持つことや、債権者と円滑にコミュニケーションを取ることが個人再生を成功させるための重要なポイントとなります。
なお、債権者が消費者金融や銀行の場合は、多くのケースで小規模個人再生に同意してくれます。
過去に個人再生手続きを行ったことがあり、規定の期間が経過していない
個人再生の手続きは、債務者が過去に一度でも手続きを行ったことがある場合、一定の制限が設けられます。
具体的には、個人再生を行った後、一定の期間が経過しないと再度の個人再生の申立てができません。
これは、債務者が再三にわたって個人再生を利用し、その都度新たな債務を生じさせることを防ぐための措置です。
規定の期間は、最初の個人再生手続きが完了し、債務が免除された日から起算されます。
この期間内に再度個人再生の申立てをすると、手続きは不成立となり、債務整理の他の方法を模索する必要があります。
そのため、過去に個人再生を経験した人は、申立てを検討する前に必ず経過期間を確認しましょう。
1回目の個人再生が給与所得者等再生であった場合は、2回目の個人再生には7年経っている必要があります。小規模個人再生には、期間のルールはありません。
 専門家から一言
専門家から一言
個人再生ができないときの対処法
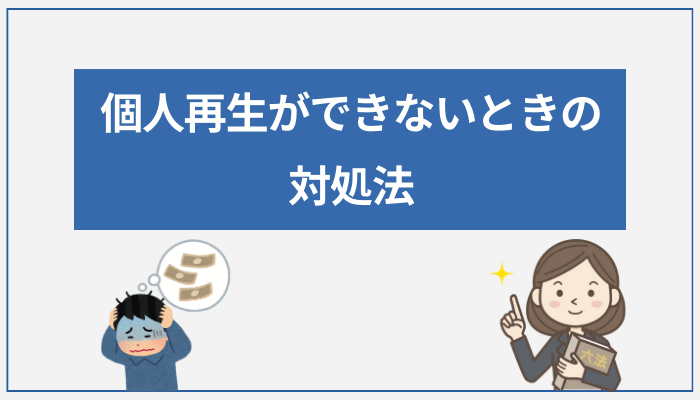
自己破産を行う
個人再生ができない場合でも、自己破産が選択肢として考えられます。自己破産とは、債務者が自らの財産を全て手放し、法的に全ての債務を免除する手続きです。
自己破産には利点と欠点があります。利点としては、破産申立後の新たな収入は債務返済に充てる必要がない点、債務が全額免除される点があります。
一方で、欠点としては、信用情報に登録される期間が長く、その間新たな借入れができない点、財産の大部分を失う点があります。
個人再生が困難な場合、自己破産について弁護士や司法書士と相談してみると良いでしょう。
任意整理を行う
任意整理も個人再生ができないときの選択肢の一つです。任意整理とは、債務者自身が債権者と直接交渉し、返済条件を再調整する手続きを指します。
返済額の減額や利息のカットなどが可能で、その結果、返済負担を軽減できる場合があります。任意整理は裁判所を介さないため、手続きがスムーズに進むことも多いです。
ただし、債権者全員と個別に交渉する必要があるため、手間がかかる点に注意が必要です。
個人再生を再度申し立てる
個人再生が一度不成立となった場合でも、一定の期間を経過すれば再度申し立てることが可能です。ただし、再度申し立てる際には、前回の不成立の原因を解消する必要があります。
例えば、返済計画が不十分だった場合は、より具体的で実行可能な計画を立てることが求められます。
また、債務の状況や収入の状況が大きく変わった場合も、再度の申し立てが考えられます。個人再生の再申立ては、弁護士や司法書士としっかりと相談することが重要となります。
経済的状況を改善するために収入を増やす
それぞれの個人再生手続きはあくまで債務解決の手段であり、根本的な解決には収入を増やし、生活の改善が不可欠です。
特に個人再生が適用できない場合、現状の収入では返済が難しいことが多いです。
そのため、アルバイトや副業を始める、資格を取得してより良い職に就くなど、収入を増やす手段を検討することが重要です。
また、支出を見直し節約することでも、手元に残る金額を増やすことができます。
個人再生の手続きを成功させるためのポイント

正確な債務総額を確認する
個人再生手続きを成功させるためにはまず、自身の借金総額を正確に把握することが重要です。すべての債権者から請求書や残高証明書を取り寄せて、全ての借入額を確認しましょう。
この作業は、返済計画を立てるための基礎となります。また、債務総額を把握することで、借金の実態を明確に理解し、再び同じ状況に陥らないようにするための学習にもなります。
弁護士や司法書士との良好な関係を保つ
個人再生の申立てには専門的な知識と経験が必要なため、弁護士や司法書士のアドバイスは非常に重要です。
定期的に連絡を取り、手続きの進行状況を確認し、必要な書類の提出などの指示をきちんと守ることが求められます。
また、借入れの状況が変わった場合や返済計画について疑問や懸念がある場合は、すぐに連絡して相談しましょう。
収入と支出を正確に記録し、現実的な返済計画を立てる
返済計画を立てるためには、自身の収入と支出を正確に把握する必要があります。それには、毎月の固定費や変動費を一覧表にまとめ、収入とのバランスを見ることが重要です。
また、優先すべき借金や返済期間、返済額などを考慮に入れた現実的な返済計画を立てることが求められます。
その計画は、自身の生活レベルを維持しつつ、返済が可能な計画でなければなりません。
新たな借入れをしない
個人再生手続き中に新たな借入れを行うことは、手続きを複雑化させ、成功の可能性を低下させます。
返済計画が承認された後でも、新たな借入れは債務整理の効果を打ち消し、負債が再び増える原因になります。
そのため、絶対に新たな借入れを行わないという意識が必要です。
手続き中も生活費をきちんと確保する
個人再生手続きは長期間に及ぶことが多く、その間も生活費は必要です。そのため、生活費を確保しながら返済計画を実行するバランスが重要です。
これを怠ると、生活に困窮し、結果として返済計画が頓挫する可能性があります。固定費を最低限に抑え、無駄な出費を削減するなど、工夫して生活費を確保するよう努めましょう。
財産の隠蔽や過大申告をしない
個人再生手続き中に財産を隠したり、過大に申告したりすることは法的に禁じられています。
また、これらの行為は信用性を損ない、個人再生手続き自体が認められなくなる可能性があります。
正直かつ公正に財産状況を開示し、法的手続きを遵守することが重要です。これにより、個人再生が成功し、再スタートを切る機会を得ることができます。
まとめ
個人再生ができないケースは様々あります。個人再生ができない場合でも、自己破産や任意整理といった他の債務整理や再度の個人再生申立てなどの選択肢があります。
個人再生を成功させるためには、債務総額を把握し現実的な返済計画を立てましょう。複雑な手続きですが、適切に行動すれば借金問題を解決させることが可能です。